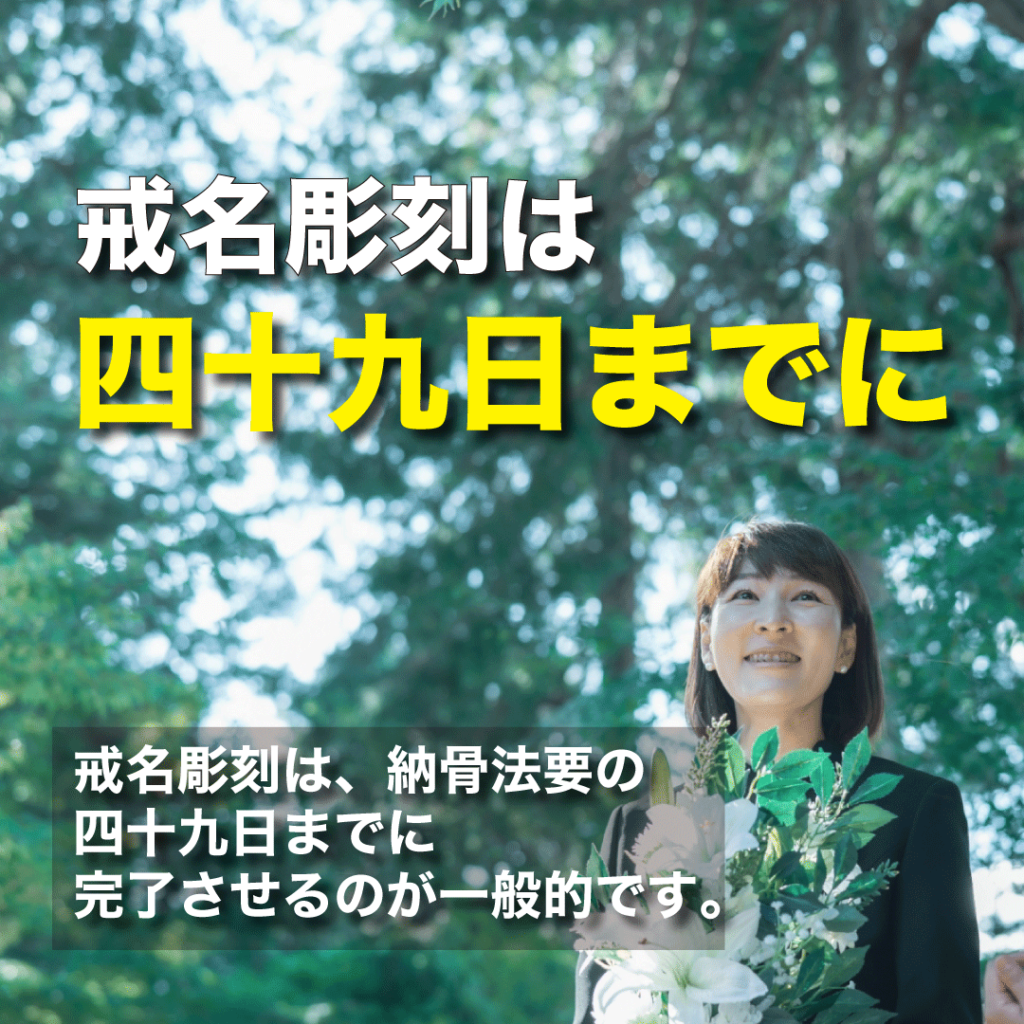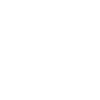\ 彫刻師への相談は無料・お気軽に/
戒名とは? 一般の人々が持つ関心と疑問

戒名(かいみょう)とは、仏教において故人に授けられる名前のことです。葬儀や供養の際に用いられるもので、仏門に入った証としての意味を持ちます。しかし、現代では「本当に必要なのか?」「高額な費用がかかるのはなぜ?」といった疑問を持つ人も増えています。本記事では、一般の人々が戒名について関心を持つポイントを詳しく解説します。
【お墓をお持ちの方へ】
意外と後で困るのが、「戒名の追加彫り」です。「お墓への文字入れ」「墓石への名入れ」などとも呼ばれていますが、この「戒名の追加彫り」は、四十九日までに行うのが一般的です。
戒名の追加彫りは通常、2週間ほど要します。早めにご手配することをお勧めします。
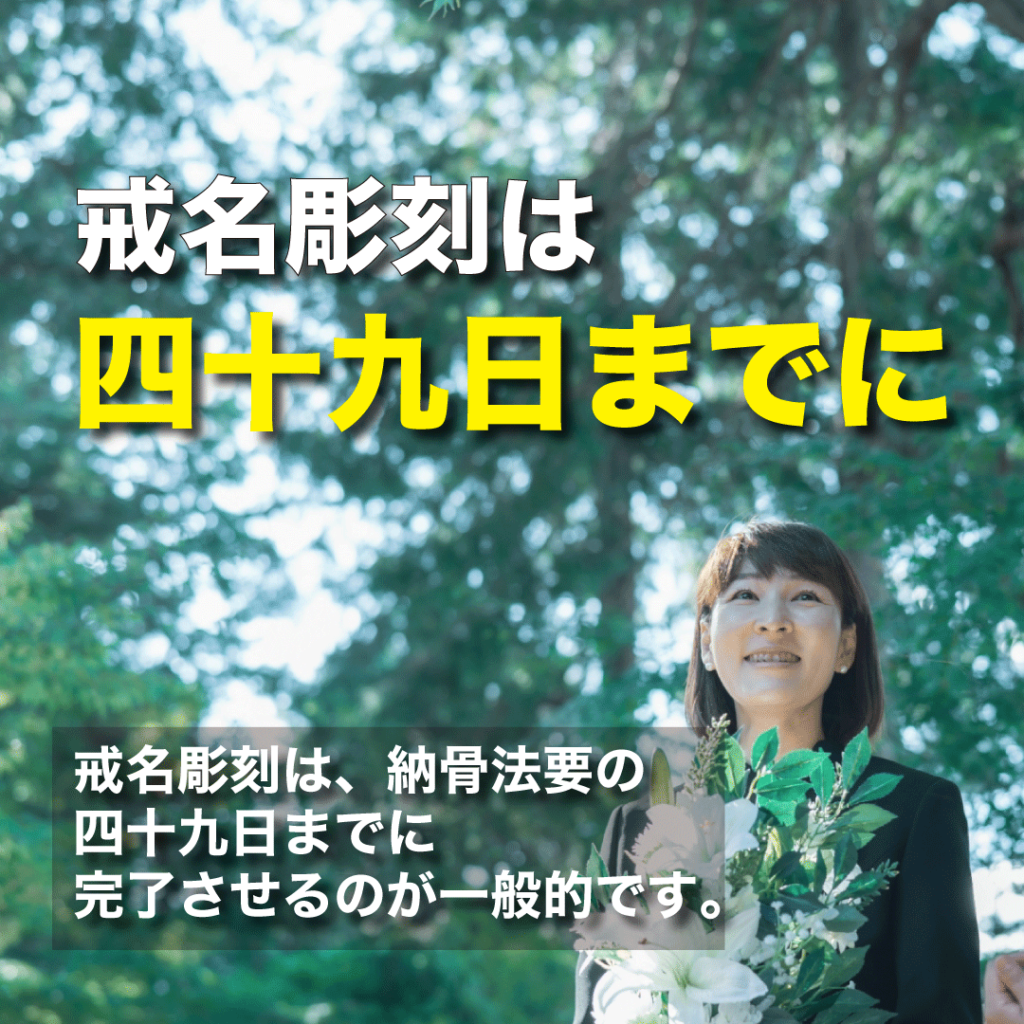
1.戒名の意味と必要性

1-1.戒名とは何か?
戒名は、仏教の信仰に基づいて故人に与えられる名前であり、死後に仏の弟子となることを象徴しています。もともとは、仏教徒が修行の証として得る名前でしたが、日本では主に亡くなった後に授かるものとなりました。
戒名には、仏教の教えに則った意味が込められており、個々の生き方や功績、性格などを反映して付けられることもあります。例えば、慈悲深い人には「慈」、学問に秀でた人には「学」などの文字が含まれることがあります。
1-2.戒名が持つ宗教的な意味
仏教の教えでは、生者と死者の境界を越えて、故人が成仏するためには戒名を通じて仏の世界へ導かれることが重要だと考えられています。また、仏の弟子として新しい名を得ることで、生前の苦しみや煩悩から解放されると信じられています。
1-3.戒名なしでも供養できるのか?
現代では無宗教の家庭も増え、「戒名がなくても問題ないのでは?」という声も聞かれます。実際に、戒名がなくても供養する方法は存在し、俗名で供養されるケースもあります。しかし、寺院や仏教徒の間では、戒名を持つことが故人の魂の安定に寄与するとされています。
また、戒名なしでの供養を選ぶと、親族や周囲の人々との意見の相違が生じることもあるため、事前に家族とよく話し合うことが重要です。
2.戒名のランクと費用

戒名は基本的に、「院号」「道号」「戒名」「位号」、4つの号で構成されています。
一万円札の顔「渋沢栄一」の戒名「泰徳院殿仁智義譲青淵大居士」を例にすると、「泰徳院殿」が院号、「仁智義譲(じんちぎじょう)」が道号、「青淵(せいえん)」が戒名、「大居士」が位号に該当します。
「戒名」は、この4つの号を組み合わせた名前全体(渋沢栄一が特別であり、10文字前後が一般的)のことです(ただし、厳密に言えば、3番目の号「戒名」で表される、2文字の部分が戒名です)。
2-1. 戒名の構成要素
①院号(いんごう)
格式の高い戒名に付けられる特別な称号として、「院殿号(いんでんごう)」と「院号(いんごう)」があります。最も高位とされるのが「院殿号」で、その次に「院号」が続きます。
「院殿号」はもともと天皇や高位の貴族のみに許された称号でした。しかし、足利尊氏(等持院殿)が用いたことがきっかけとなって、武家や大名の間でも広まったと言われています。「院殿号」は本来は「院号」より下位の称号ですが、文字数が多く豪華な印象を与えることから、現代では「院号」よりも上位とされることが一般的です。
一方、「院号」は平安時代、嵯峨天皇が御所を「嵯峨院」と名付けたことに由来しています。元々は寺院の建立者を敬うための称号でしたが、次第に戒名としても用いられるようになりました。現在では、寺院に多大な貢献をした人や高い身分の人、顕著な功績を残した人に授けられることが多く見受けられます。
②道号(どうごう)
故人の信仰や生き方を象徴する言葉であり、仏教の教えや徳を表す漢字が選ばれるのが一般的です。
「道号」は、本名とは別に用いられる別名としての意味を持ち、生前にペンネームとして使用されることもあります。
現代では、故人の趣味や性格、特徴を反映させた漢字を選び、その人らしさを表現する目的で使われることが多くなっています。ただし、水子や幼児、未成年者には道号は付けられず、また浄土真宗では本来使用されません。
| 道号でよく使われる文字 | |
| 性格や趣味を表す文字 | 光、翁、老 |
| 場所や地域を表す文字 | 海、山、峰、峯、雲、月 |
| 住居を表す文字 | 宅、殿、斎 |
③戒名(本名の部分)
「戒名(かいみょう)」とは、故人が仏の弟子として成仏することを示すために与えられる名前であり、極楽浄土での名前です。宗派によっては「法号」や「法名」とも呼ばれます。
戒名は通常、道号に続く二文字で構成され、故人の俗名から一文字、仏教に由来する教えや仏様の名から一文字を取って名付けられます。また、故人の生前の職業や人柄、尊敬していた人物にちなんだ漢字が選ばれることもあります
| 戒名でよく使われる文字 | |
| 生前の名前(俗名)の文字 仏様の名前や経典の文字 故人が尊敬する人に関連する文字 故人の生前の職業を連想する文字 先祖代々受け継いでいる文字 |
④位号(いごう)
「位号(いごう)」とは、戒名の末尾に付される称号で、仏教における身分や立場を表すものです。
現代の「様」という敬称に近い役割を持ち、仏教徒としての位階を示します。
この位号は、故人の信仰の深さや社会的な貢献度、立場などを考慮して決められ、性別によって呼称が異なります。男性には「士」という侍を意味する文字が、女性には「女」や「姉」が用いられるのが特徴です。
一般的には、「信士(しんじ)」や「信女(しんにょ)」が用いられることが多いですが、これらは単に標準的な称号であり、故人の価値や功績を低く評価しているわけではありません。
| ランク | 男性の位号 | 女性の位号 |
|---|---|---|
| 上位 下位 | 大居士(だいこじ) | 清大姉(せいたいし) |
| 居士(こじ) | 大姉(たいし) | |
| 大禅定門(だいぜんじょうもん) | 大禅定尼(だいぜんじょうに) | |
| 禅定門(ぜんじょうもん) | 禅定尼(ぜんじょうに) | |
| 清信士(せいしんじ) | 清信女(せいしんにょ) | |
| 信士(しんじ) | 信女(しんにょ) |
未成年の子どもの位号は、年齢や性別に応じて異なります。死産した子どもには「水子」が使われ、5歳以下の子どもには「嬰児・嬰女」や「孩児・孩女」、15歳以下では「童子・童女」が一般的に用いられます。
ただし、実際には未成年でも「信士」や「信女」が使われることもあるため、家庭や菩提寺と相談して決定することが望ましいでしょう。
| 年齢 | 男の子の位号 | 女の子の位号 |
|---|---|---|
| 死産 | 水子 | |
| 5歳以下 | 幼児・嬰児・孩児 | 幼女・嬰女・孩女 |
| 15歳以下 | 童子・大童子・禅童子 | 童女・大童女・禅童女 |
2-2. 戒名のランク
戒名にはいくつかのランクがあり、ランクによって内容や費用が異なります。以下は主なランクの特徴と費用の目安です
①釈号(しゃくごう)
「釈○○」の形を取る、最も一般的な戒名です。多くの人に利用されており、比較的安価な戒名です。
費用目安:10万~30万円
②院号付き戒名
「○○院○○居士/大姉」のように院号がつく戒名は、故人が社会的、宗教的に高い評価を得ていた場合に授けらる傾向にあります。
費用目安:50万~100万円以上
③特別な称号付き戒名
故人が寺院に多大な貢献をした場合や、特別な業績を残した場合、さらに特別な院号や道号が付与されることがあります。先に紹介した渋沢栄一はその一人です。
費用目安:100万円以上(要相談)
3.戒名の決め方と変更

3-1.戒名の決め方
戒名は本来、お寺や僧侶が故人の人生や功績を考慮して授けるものですが、最近では自分で希望を伝えることも可能になっています。特に、生前に戒名を決めておく「生前戒名(寿陵)」という方法が注目されており、自分で意味のある戒名を選び、納得のいく形で決めることができます。
3-2.戒名を決める際のポイント
①宗派に適した戒名を選ぶ(宗派ごとに特徴が異なる)
戒名は仏教の宗派によって用いる漢字や形式が異なります。例えば、浄土真宗では「釋」の字を用いるのが一般的であり、禅宗では「道」や「玄」の字が含まれることが多いです。そのため、故人の宗派に合わせた戒名を選ぶことが重要です。誤った戒名をつけると、供養の際に問題が生じる可能性があるため、事前に菩提寺や専門家に相談しましょう。
②人生の功績や個性を反映させる(学業・仕事・趣味など)
戒名は単なる名前ではなく、故人の生前の歩みや人柄を表すものでもあります。例えば、学問に秀でた人には「学」、慈悲深い人には「慈」といった漢字を含めることが一般的です。また、趣味や特技にちなんだ漢字を入れることで、より故人らしい戒名にすることも可能です。
③家族と相談して納得のいくものにする(後々のトラブルを防ぐ)
戒名は故人にとって大切なものですが、家族にとっても重要な決定事項です。戒名のランクや内容について家族と事前に話し合い、納得のいく形で決めることで、後々のトラブルを防ぐことができます。また、家族が納得しやすいように、戒名の意味や由来を僧侶に説明してもらうのも一つの方法です。
3-3.戒名の変更は可能か?
戒名がすでに付けられた後に、「思っていたものと違う」「別の意味の戒名にしたい」と思うこともあります。この場合、変更自体は可能ですが、追加の費用がかかることが一般的です。
また、お寺によっては変更を認めない場合もあるため、事前に慎重に決めることが大切です。
4.戒名をつけるタイミング
戒名は一般的に葬儀の際に授けられますが、四十九日法要までにつけるのが一般的とされています。ただし、近年では生前に戒名を準備する「寿陵(じゅりょう)」の考え方も広まりつつあり、早めに準備することで遺族の負担を軽減することができます。
また、四十九日を過ぎても戒名をつけることは可能であり、何らかの事情で遅れた場合でも問題ありません。
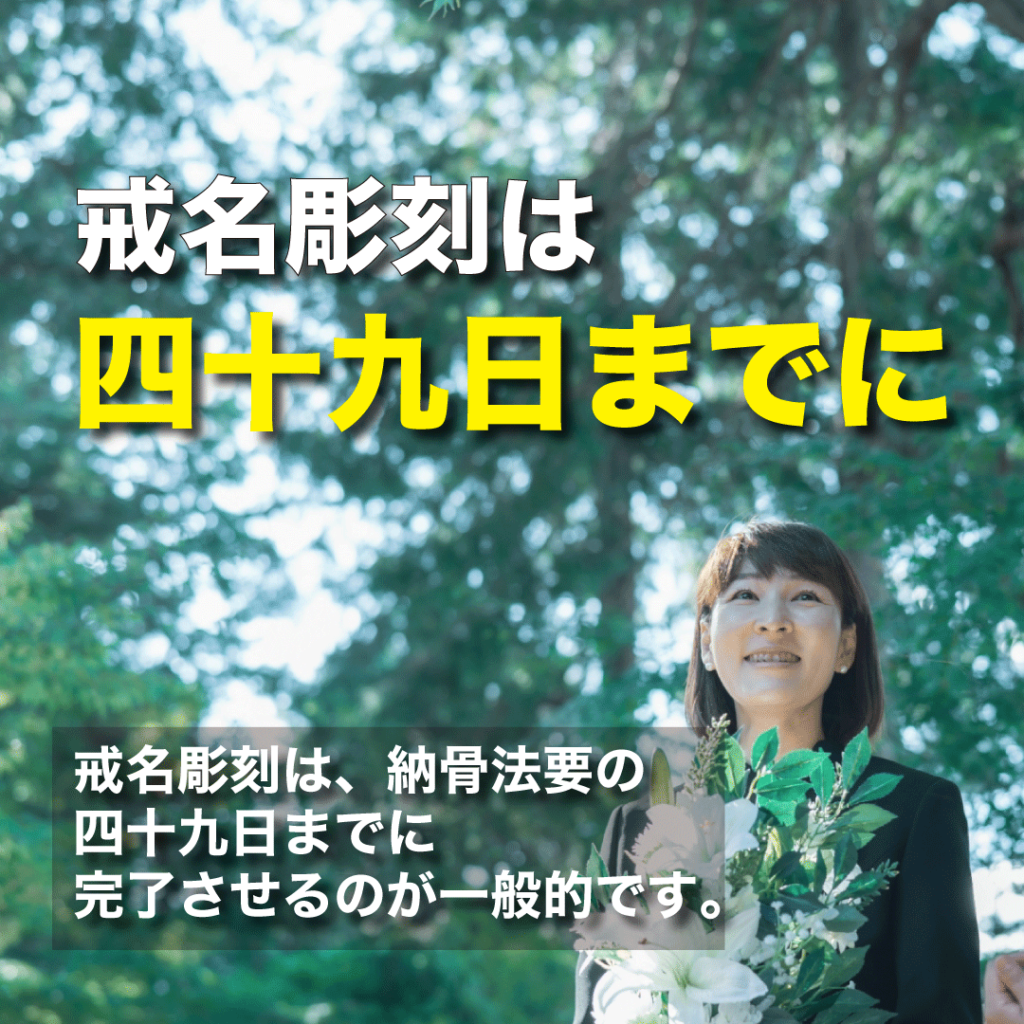
5.宗派による戒名の違い
宗派によって戒名の考え方や呼び方が異なります。例えば、浄土真宗では「戒名」ではなく「法名」と呼びます。日蓮宗では、戒名の中に「日」の字が入ることが多い傾向にあります。また、曹洞宗や臨済宗では、禅宗の影響を受けた独自の戒名体系があります。
このように、宗派によって戒名の付け方に違いがあるため、自分の宗派の習慣を知っておくことは非常に大切です。
6.戒名なしでも問題ないのか?
近年、「俗名墓」と呼ばれる戒名なしの墓石を選ぶ人が増えています。戒名がなくても供養自体は可能であり、無宗教の家庭ではこのスタイルを選ぶこともあります。
戒名なしの供養が増えている理由として、
①費用を抑えられる(戒名の費用を省略できる)
②無宗教の人が増えている(宗教にこだわらない供養方法の選択)
③自由な供養の形を求める人が増加(個人の価値観を重視)
などがあります。
いずれにせよ、戒名がない場合でも、しっかりと供養をすることで故人を偲ぶことは可能です。
7.まとめ
戒名は仏教の伝統として重要な意味を持ちますが、現代ではその必要性について議論されることも増えています。戒名をつけるかどうか、どのような戒名を選ぶかは、故人や家族の価値観による部分が大きく、慎重な検討が必要です。
また、近年では俗名のまま供養をするケースも増えており、その選択肢も認められつつあります。ただし、宗派や家族の意向を踏まえた上で決定することが望ましいでしょう。戒名のランクや費用、変更の可否なども含め、事前に十分な情報を集め、後悔のない形で供養の準備を進めることが大切です。